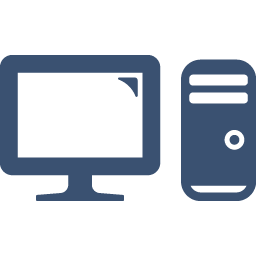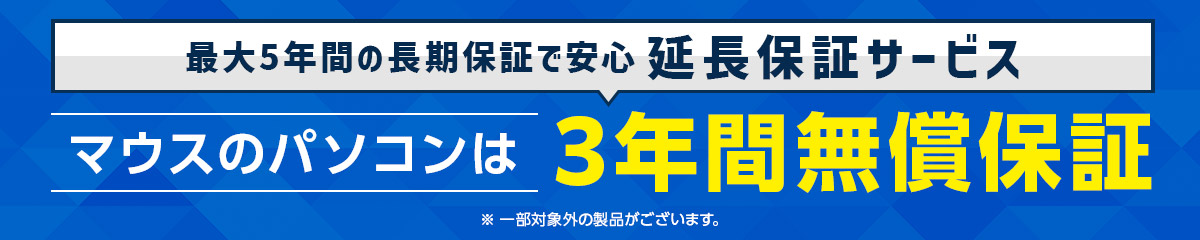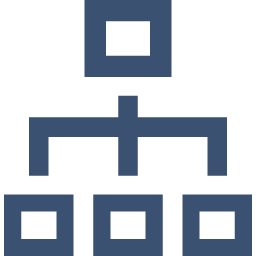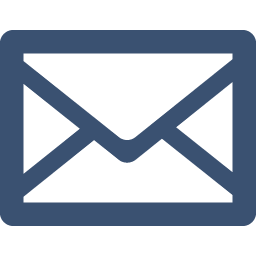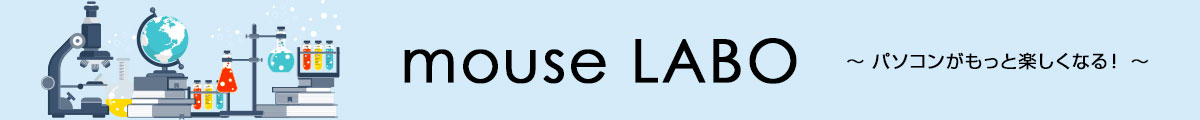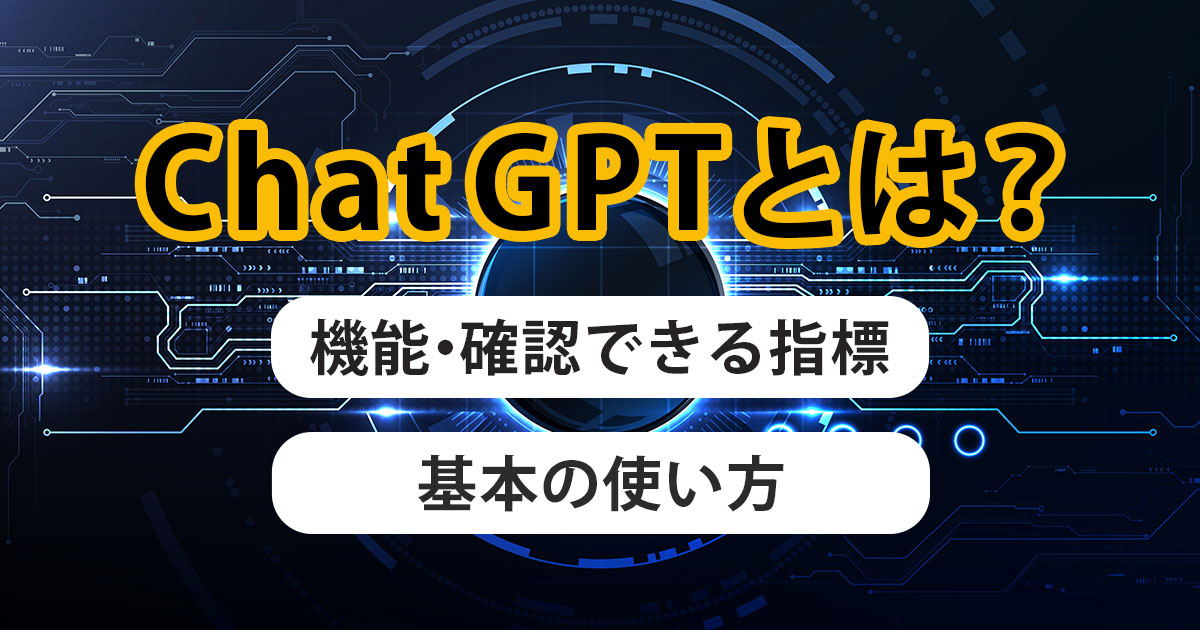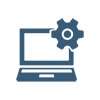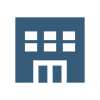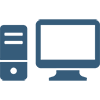ChatGPTは、人間のような自然な会話ができるAI(人工知能)サービスです。文章作成やプログラミング、データ分析など幅広い業務に活用でき、作業効率の向上や新しいアイデアの創出をサポートしてくれます。
例えば、ビジネスシーンでは企画書の作成や市場分析、教育分野では学習サポートなど、用途は多岐にわたります。ただし、効果的に活用するには、ChatGPTの仕組みや機能、使い方を理解しておくことが大切です。
この記事では、ChatGPTの概要や無料版と有料版との違い、利用方法、注意点などをわかりやすく解説します。ぜひ参考にしてください。
※ パソコンの構成によっては、操作方法が一部異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
- OpenAIによって開発されたChatGPTとは?
- ChatGPTの仕組み
- ChatGPTを活用するメリット
- ChatGPTでできること
- ChatGPTのモデルを簡単に紹介
- ChatGPTの無料版・有料版の違い
- ChatGPTの始め方とは?アカウント作成・日本語設定・使い方を解説
- ChatGPTを使う際の注意点
- まとめ:ChatGPTを仕事や趣味に活用してみよう!
OpenAIによって開発されたChatGPTとは?
ChatGPTは、アメリカのOpenAI社が開発した対話型AI(人工知能)サービスです。2022年11月にGPT-3.5がリリースされ、自然な会話形式で質問に答えたり、文章を作成したりできるAIとして注目を集めました。さらに、2023年3月にはGPT-4.0が、2024年5月にはGPT-4oがリリースされ、より高精度なAIサービスに進化しています。
2024年11月現在では、音声でのやり取りや画像生成に対応できるようになり、活用の幅がより広がりました。また、有料プランに入ることで利用できるChatGPT APIを活用し、ChatGPTを使ったサービスを開発する企業も出てきています。
ChatGPTの仕組み
1.事前学習を行い言語モデルを構築する
2.特定の分野に特化させるファインチューニングを行う
3.Reward Model(報酬モデル)による評価やユーザーのフィードバックをもとに改善を行う
基本となるのは事前学習と呼ばれる処理で、インターネット上の大量のテキストデータを学習します。この際、AI自身が問題の作成・回答を繰り返す、「自己教師あり学習」という方法を採用しており、自立的に自然言語を学習していきます。
また、大量のデータを高速で学習するために利用されている技術が「ディープラーニング」です。ディープラーニングは、人間の脳の仕組みを模倣しており、膨大なデータ量を素早く学習できます。
ChatGPTでは、ディープラーニングの一種として、文章の前後関係を理解して次に来る言葉を予測する仕組みの「Transformer」と呼ばれるモデルが採用されています。
次に行われるのが、目的に合わせてパラメータを調整し、回答の精度を高める「ファインチューニング」です。たとえば、医療や法律などの特定の分野に特化する際に重要となります。
その後、「Reward Model」によって生成した文章を評価・改善し、リリース後もユーザーからのフィードバックを参考に改善を繰り返していきます。
ChatGPTを活用するメリット
ChatGPTの活用により、さまざまなメリットが得られます。たとえば、文章作成の下書きや校正にChatGPTを活用することで、作業時間を短縮できます。
企画書やプレゼン資料の作成では、アイデア出しから文章の推敲までできるため、効率よく仕事を進められるでしょう。学習面では、わからない問題の解説を依頼したり、苦手分野の学習方法を相談したりできるため、効率的に学習を進められます。
また、新規事業の立ち上げやマーケティング戦略の策定で、新しい視点やアイデアが生まれやすくなることもメリットです。さらに、OpenAIが提供するAPIを利用すれば、自社システムやアプリケーションにChatGPTの機能を組み込むこともできます。
これにより、カスタマーサポートの自動応答や社内の業務効率化など、用途に応じた活用が可能です。
ChatGPTでできること
ChatGPTは、幅広い用途に活用できるAIサービスです。日常業務や学習、開発など、さまざまな場面で活用できます。具体的な機能と活用方法は次のとおりです。
| 活用方法 | 具体例 |
| アイデア出し | ・壁打ちをして新しい発想を引き出す ・企画立案や問題解決のアイデアを提案する |
| ライティングサポート | ・文章の校正や推敲をする ・企画書の下書きを作成する |
| テキストの加工 | ・長文を要約する、要点をまとめる ・翻訳を行う |
| Excel作業の効率化 | ・関数やマクロの作成をサポートする ・データ処理の方法を提案する |
| プログラミング支援 | ・コードの作成や修正をサポートする ・エラーの原因を解析して解決策を提示する |
| チャットボット開発 | ・APIを利用して独自のチャットボットを作成する ・自社サービスに合わせた応答を設定する |
| データ分析 | ・データの傾向や特徴を分析する ・グラフや表を用いた可視化を行う |
ChatGPTのモデルを簡単に紹介
ChatGPTは複数のモデルが提供されており、用途に応じて選択できます。処理能力や対応する機能が異なるため、目的に合わせて適切なモデルを選びましょう。各モデルの主な特徴は次のとおりです。
| モデル名 | 特徴 | コンテキスト ウィンドウ (一度に処理できる情報量) |
最大出力 トークン (一度に出力できるテキスト量) |
トレーニング データ |
| GPT-4 | ・テキスト生成、要約、翻訳、質問応答など言語処理タスクに優れている ・テキスト、画像の入力が可能 ・OpenAI APIが利用できる |
8,192トークン | 8,192トークン | 2021年9月まで |
| GPT-4o | ・「GPT-4」の後継モデル ・「GPT-4」よりも回答速度が向上 ・テキスト、画像、音声のリアルタイム入力と出力が可能 テキストにおいて英語以外の言語性能が改善 |
128,000トークン | 4,096トークン | 2023年10月まで |
| GPT-4o mini | ・「GPT-4o」の軽量、高速化モデル ・より低コストで利用できる ・出力の品質は「GPT-4o」より劣る |
128,000トークン | 16,384トークン | 2023年10月まで |
| OpenAI o1-preview | ・科学、コード生成、数学などの分野の複雑なタスク処理に優れている ・複雑な問題に対して時間をかけて考え、回答を生成する |
128,000トークン | 32,768トークン | 2023年10月まで |
| OpenAIo1-mini | ・「OpenAI o1-preview」より小型、安価モデル ・特に数学やコーディングに適している ・非STEM(科学、技術、工学、数学)トピックには弱い |
128,000トークン | 65,536トークン | 2023年10月まで |
ChatGPTの無料版・有料版の違い
ChatGPTは無料版と有料版(ChatGPT Plus)で利用できる機能が異なります。より高度な機能を利用できる有料版は、月額20ドルです。無料版でもGPT-4o miniが利用でき、文章作成や質問回答などの基本的な機能は十分に活用できます。
しかし、無料版には次のような制限があります。
・GPT-4oの利用回数に制限がある
・GPT-4・OpenAI o1-preview・OpenAI o1-miniが使用できない
・生成に時間がかかる
・新機能への早期アクセスができない
また、有料版は次のような機能を利用できます。
| 機能名 | 概要 |
| メモリ機能 | ・過去の会話を保存できる ・続きから対話を再開できる |
| カスタムGPT(GPTs) | ・目的に特化したカスタムAIを開発できる ・開発したカスタムAIを共有・公開できる ・APIで外部サービスと連携できる |
| Advanced Voice Mode |
・音声での対話が可能 |
| 画像生成 | ・DALL-E 3による高品質な画像を生成できる ・プロンプト(指示文)で画像のイメージを伝えられる |
| データ分析 | ・Google Drive・OneDriveのファイルをアップロードできる ・インタラクティブな表やグラフ作成、カスタマイズしたグラフのダウンロードができる |
有料版は多様な機能が使えることに加え、待ち時間が少なく安定した速度で利用できます。業務での使用や継続的な利用を考えている方は、有料版の導入を検討するとよいでしょう。
法人契約プランもある
ChatGPTには法人向けの契約プランとして、Team版とEnterprise版があります。Team版は1ユーザーあたり月額30ドル(年額25ドル)で、複数のチームメンバーでワークスペースを共有できます。(※価格は2024年11月16日時点のものです。)
Enterprise版は大企業向けのプランで、利用料金は条件によって異なるため問い合わせが必要です。高度なセキュリティ機能や管理機能、無制限の高速アクセス、高度なデータ解析などに対応しています。プランの選択は、利用人数や予算、必要な機能に応じて検討するとよいでしょう。
どちらのプランも業務効率の向上やセキュリティ強化などに役立つため、事業規模に合わせて検討してみてください。
ChatGPTの始め方とは?アカウント作成・日本語設定・使い方を解説
ChatGPTは、アカウントを作成してログインすることで始められます。ここでは、パソコンからChatGPTを始める手順を紹介します。
1.Google検索で「ChatGPT」を検索する
2.公式サイト(chat.openai.com)を開く
3.右上の「Sign up(サインアップ)」をクリックする
4.アカウント作成画面になるので、メールアドレスを入力して「続ける」をクリックするか、GoogleやMicrosoft、Appleのアカウントで作成する
5.パスワードを設定(12文字以上) すると、登録したアドレスにOpenAIからメールが届く
6.メールを開き名前・電話番号を登録する
7.認証コードが記載されたショートメールが届くので、確認後にChatGPTの公式サイトで入力するとアカウント作成が完了し、利用できるようになる
8.言語が日本語以外になっている場合、画面右上のアカウントマークをクリックし、設定から言語を選択すると変更できる
ChatGPTの使い方は簡単です。中央の入力欄に質問や指示を入力し、Enterキーまたは右の送信ボタンをクリックすると、回答が生成されます。
より具体的な回答が欲しい場合やほかの質問をしたい場合は、再度入力欄にプロンプトを入力して質問しましょう。なお、スマートフォンアプリでも始め方はおおむね同じです。
ChatGPTを使う際の注意点
ChatGPTは便利なサービスですが、使用する際には次の点に注意しましょう。
1.情報の正確性をチェックする
2.生成された内容が倫理的に問題がないか確認する
3.個人情報や機密情報は入力しない
4.著作権侵害に該当しないか確認する
各注意点の詳細を解説します。
1.情報の正確性をチェックする
ChatGPTの回答は、必ずしも正確な情報とは限りません。たとえば、技術的な質問に対して古い情報を回答したり、事実と異なる内容を提示したりすることがあります。
これは、学習データの期間外または範囲外の質問をした際に発生しやすくなるため、注意が必要です。ただし、検索エンジンと連携できるChatGPT searchを使用すると、最新情報を参照できます。
ChatGPT searchは、2024年11月現在では有料プランでのみ使用できますが、無料プランでも提供する予定と発表されています。
ChatGPTなどのAIサービスで生成された情報は、公式サイトや信頼できる情報源で事実確認を行うようにしましょう。
2.生成された内容が倫理的に問題がないか確認する
ChatGPTは倫理的に問題のある回答を生成しないよう設計されていますが、プロンプトの与え方によっては不適切な表現や内容を含むことがあります。たとえば、差別的な表現や誤解を招く文章が含まれる恐れがあるため注意が必要です。
生成された文章はそのまま使用せず、表現や文脈を見直しましょう。具体的には、公序良俗に反しないか、他者への配慮が適切かなどを確認します。
ChatGPTはあくまでも文章作成の補助ツールとして活用し、内容に対する最終的な判断は人が行いましょう。
3.個人情報や機密情報は入力しない
ChatGPTに入力した情報は、AIモデルの学習データとして使用されることがあります。たとえば、氏名や住所、電話番号などの個人情報を入力すると、ほかのユーザーへの回答に含まれる恐れがあるため要注意です。
また、OpenAIのスタッフが入力内容を確認することもあります。企業で利用するときは、社内の機密情報や顧客情報を入力しないことも大切です。業務で使用する場合は、情報セキュリティポリシーを定め、入力可能な情報の範囲を明確にしましょう。
4.著作権侵害に該当しないか確認する
ChatGPTで生成したコンテンツも、著作権法の対象です。ChatGPTはWeb上の著作物を学習しているため、既存のコンテンツに酷似した文章や画像、プログラムを生成することがあります。
生成されたコンテンツの著作権は利用者にありますが、ほかの著作物と酷似している場合は著作権侵害となる恐れがあるため注意が必要です。そのため、生成された内容はそのまま使用せず、Web上に類似コンテンツがないか確認し、適切に編集・改変して利用しましょう。
まとめ:ChatGPTを仕事や趣味に活用してみよう!
ChatGPTは、日常生活やビジネスシーンで活用できる便利なAIツールです。文章作成やプログラミング、データ分析、画像生成など、幅広い用途に対応します。
無料版でも基本的な機能を利用でき、有料版ではより高度な機能を活用できます。ただし、生成された情報の正確性や倫理面には注意が必要です。個人情報や機密情報は入力を避け、著作権にも配慮しましょう。
まずは、記事内で紹介した手順を参考にアカウントを作成し、疑問の解消や文章作成に活用してみてください。
ChatGPTのようなAIモデルは主にクラウド上で処理されていますが、ローカルでのAIサービスの利用には高い処理性能が求められることがあります。マウスコンピューターでは、AIタスクの効率化に役立つNPUを搭載した「AI PC」を販売しています。クリエイター向けAI PCや、ビジネス向けAI PCは、ぜひマウスコンピューターでお求めください!