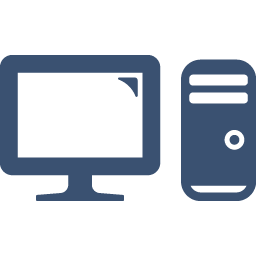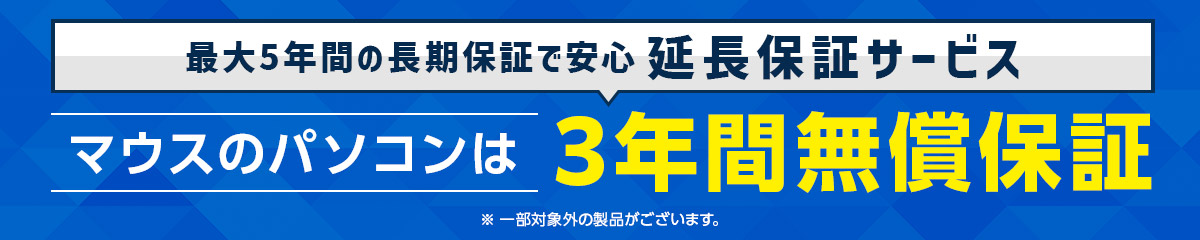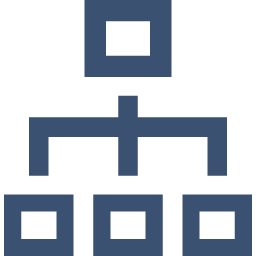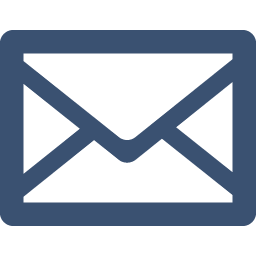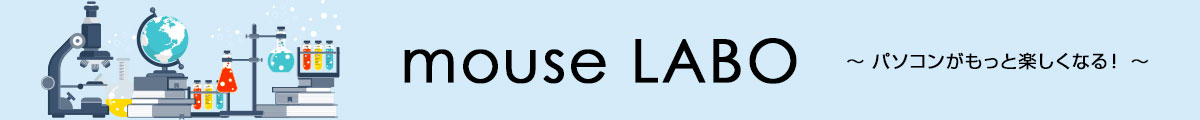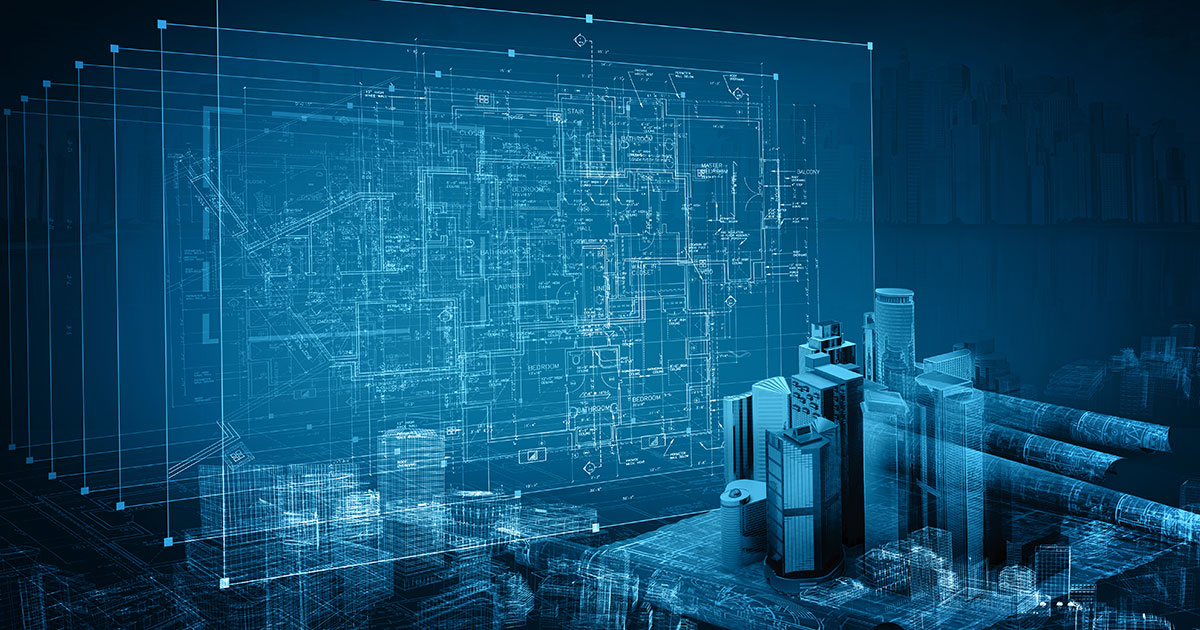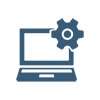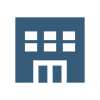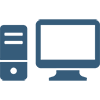BIM/CIMは、建築・建設業の調査・計画・設計から施工・維持管理までのプロセスを効率化する手法です。3次元モデルを基盤とし、情報を一元管理することで業務効率や品質の向上が期待できます。
2023年度から国土交通省が定める、大規模な設計ではBIM/CIMの原則適用が開始され、建築・建設関連に従事する方はその活用方法や要件を理解することが求められています。
この記事では、BIM/CIMの基本概念やメリット、実務での活用例をわかりやすく解説します。BIM/CIMの導入を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
※ 製品の情報や価格は2026年1月13日時点の情報となります。
- BIM/CIM(ビム/シム)とは?概要をわかりやすく解説!
- BIM/CIMの導入により解消が期待されている課題
- BIM/CIM導入により期待できる効果
- BIM/CIMの具体的な活用シーン
- BIM/CIMをより高度に活用するための「点群データ」とは?
- BIM/CIMの情報収集に役立つWebサイト(国土交通省・JACICなど)
- BIM/CIMの導入を検討する際の注意点
- BIM/CIMの活用におすすめ!マウスコンピューターのパソコン・ワークステーション3選!
- まとめ:BIM/CIMを活用した業務の効率化を目指そう!
BIM/CIM(ビム/シム)とは?概要をわかりやすく解説!
まずは、BIM/CIMの概要として、基本概念や目的、構成要素、BIM・CIM・3DCADの違いや義務化について解説します。
1|BIM/CIMの基本概念と目的
BIM/CIMはデジタルを活用し、建築・建設プロジェクトの調査・計画・設計から施工・維持管理までのプロセスを効率化する手法です。構造物を立体的に表現した3次元モデルを基盤に、建物やインフラの詳細な情報を統合・管理します。
BIM/CIMを活用する目的は、プロジェクトの透明性を高め、品質や生産性を向上させることにあります。たとえば、3次元モデルを用いることで施工中の問題を未然に防いだり、関係者間のコミュニケーションを円滑にしたりすることが可能です。
また、維持管理の段階でもモデルに記録された情報を活用できるため、長期的な効率化・コスト削減効果が期待できます。このように、BIM/CIMは建設業界のデジタル化を進める重要な手法です。
2|BIM/CIMモデルの構成要素
BIM/CIMモデルは、建築物やインフラのデジタル情報を統合したデータ基盤で、次の3つの構成要素から成り立っています。
・3次元モデル
建築物や構造物を視覚化する3Dデータ。寸法や形状を正確に把握できる設計の基盤となる
・属性情報
各パーツの材質・性能・数量・品質記録・点検記録・補修履歴などの詳細情報を指す。たとえば、壁材や配管の種類などが記録されている
・参照資料
2次元の図面・仕様書などの機械判読ができない資料を指す。プロジェクト全体の計画を補完する
これらは単独ではなく連携して使用され、建築・建設全体の効率化を支えます。たとえば、属性情報を使うことで、特定の部品の交換時期を把握でき、維持管理がスムーズになるでしょう。
また、参照資料と3次元モデルを組み合わせることで、設計ミスを未然に防げます。BIM/CIMは単なる設計ツールではなく、建築・建設業全体をサポートする包括的な情報基盤です。
3|BIM・CIM・3DCADの違い
BIMとCIMは、対象にしている分野が異なります。BIMは建物における情報のモデル化を指し、Building Information Modelingの略称です。一方、CIMは建物以外(トンネルやダムなど)の情報のモデル化を指し、Construction Information Modelingの略称となります。BIMは建築の分野、CIMは土木の分野と分類されていましたが、国土交通省により建設業全体を指すものとして、BIM/CIMに名称変更されました。
3DCADにおいては、建造物の形状を3Dで作成する点はBIM/CIMと同じですが、手順が異なります。3DCADはまず2Dの図面を作成後に3Dの図面を作成しますが、BIM/CIMでは初めから3Dの図面を作成し、必要に応じて2Dの図面に切り取るという流れです。また、3DCADは設計段階でのモデリングに焦点をあてており、BIM/CIMは設計から維持管理までの全体を一元管理することに焦点をあてている点も異なります。
4|BIM・CIM・3DCADの違い
2023年4月から、国土交通省はBIM/CIMの原則適用を開始しました。この義務化は、建設業界のデジタル化の推進や、施工ミスの削減、業務効率化を目指すための取り組みです。具体的な適用範囲は、設計段階ではBIM/CIM活用が必須となった一方、維持管理段階での適用は推奨にとどまっています。
義務化の詳細は次のとおりです。
義務項目や推奨項目の設定は発注者が行い、3次元モデルの作成は受注者が行います。
| 項目 | 測量:地質・土質調査 | 概略設計 | 予備設計 | 詳細設計 | 工事 |
| 義務項目 | ー | ー | ー | 〇 | 〇 |
| 推奨項目 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
※ 推奨項目は1つ以上に取り組むことを目指す
BIM/CIMの導入により解消が期待されている課題
BIM/CIMの導入は、建設業のさまざまな課題を解消する手段といわれています。特に、各プロセスにおける非効率な業務を改善することが期待されています。
BIM/CIMにより解消が期待されている、主な課題は次のとおりです。
| プロセス | 概要 | 課題 |
| 測量 | 測量機器を使い地表の形状を測定する | ・測量機器を設置・撤去させながら測定するため重労働になる |
| 地質調査 | 地中の状況を図面化する | ・地質の調査地点の選定が難しい ・地質図の作成に時間がかかる |
| 計画・設計 | 建設する場所や構造物の形状を検討・決定する | ・部材や構造物の干渉の確認にはスキルが求められ、時間もかかる ・部材、材料の数量算出に時間がかかる |
| 施工 | 構造物を建設する | ・労働災害が起きる ・施工計画の作成にスキルが求められ、時間もかかる ・部材や構造物の干渉確認にスキルが必要で、時間もかかる |
| 維持管理 | 構造物を点検・記録して修繕を行う | ・施工時の資料が適切に管理されておらず、不具合発生時の原因追及が難しい ・完成後に点検や補修ができない箇所が出てくる |
BIM/CIM導入により期待できる効果
BIM/CIMの導入により期待できる効果は、次のとおりです。
・生産性の向上が期待できる
・情報共有の速度・精度が向上する
・働き方の改善につながる
・建設業界の将来的な変革につながる
それぞれ詳しく解説します。
1|生産性の向上が期待できる
BIM/CIMは、3次元モデルの活用や情報の一元管理による生産性の向上が期待されています。そのために効果的な手法として、「フロントローディング」と「コンカレントエンジニアリング」があります。
フロントローディングとは、プロジェクトの初期段階でリソースを集中投入し、問題を未然に防ぐ手法です。これにより、仕様変更や手戻りを未然に防止し、品質向上や納期短縮が期待できます。
コンカレントエンジニアリングは、複数のプロセスを並行して進める手法のことです。たとえば、設計チームと施工チームが同じモデルを使い、同時並行で調整することで工期短縮やコスト削減が実現します。
このように、BIM/CIMの導入は建築・建設プロジェクト全体を効率化できる手法の実現につながります。
2|情報共有の速度・精度が向上する
BIM/CIMの導入により、情報共有の速度と精度が向上します。建設業界では、事業の規模が大きいほど多岐にわたる関係者との合意形成が必要です。
建設プロセスが進むにつれて変更が難しくなるため、早い段階で正確な情報共有が求められます。
BIM/CIMで作成された3次元モデルや属性情報は、パソコンで確認できるため情報伝達の遅延が発生しません。また、3次元モデルを基盤に情報が視覚化されるため齟齬が生まれづらく、関係者は正確な情報を基に業務を進行できます。結果的に、プロジェクト全体の効率化にもつながるでしょう。
3|働き方の改善につながる
建築・建設業界の課題として挙げられるのが、労働環境の過酷さや人材不足です。BIM/CIMの導入は、これらの問題を解決する手段としても期待されています。
具体的には、BIM/CIMにより生産性を高めることで、長時間労働の削減や業務負担の軽減が期待されます。
たとえば、設計段階で正確なモデルを作成することで、施工現場での仕様変更やミスを削減し、効率的な作業を実現します。これにより、週休2日制の実施やコスト削減による給与の向上が期待できるでしょう。また、リモートワークや多様な働き方にも対応できるようになり、従来の現場中心の働き方を見直す機会にもなります。
4|建設業界の将来的な変革につながる
BIM/CIMの導入は、建設業界の将来的な変革を促進します。たとえば、3次元での測量にドローンや準天頂衛星システムを活用することで、測量の精度と効率が向上します。
また、BIM/CIMモデルに基づく施工により蓄積するデジタルデータの活用により、新技術の導入拡大も期待できます。新たな技術を創出することで、工期短縮や安全性の向上が期待できるでしょう。さらに、維持管理の段階においては、ロボットやセンサーにより管理状況をデジタルデータ化し、的確な維持管理の実施が可能です。
このように、BIM/CIMは建設業界のデジタル化を進め、次世代の建設プロセスを支える基盤になります。
BIM/CIMの具体的な活用シーン
BIM/CIMの具体的な活用シーンを、設計段階・施工段階・維持管理段階に分けて詳しく解説します。
1|設計段階での活用
設計段階で建物やインフラを3次元モデルで可視化することで、関係者間の協議や合意形成を迅速に進められます。
たとえば、完成形をリアルに視覚化することで、図面だけでは伝わりにくい情報を共有し、誤解を防げます。関係者への説明会で理解が得やすくなり、迅速な合意形成が可能です。また、BIM/CIMを使えば部材や材料の数量算出作業が自動化され、効率的かつ正確に資材計画を立てられます。設計の精度が上がるだけでなく、作業時間の短縮も可能です。
このように、BIM/CIMは設計段階での合意形成と業務効率化に活用されます。
2|施工段階での活用
BIM/CIMは、施工段階における施工計画・工程管理の効率化や、安全管理の向上に活用されます。
具体的には、3次元モデルを使用して施工計画や手順をシミュレーションし、工程管理を効率化できます。たとえば、施工対象を可視化すれば、作業の進捗状況をリアルタイムで把握でき、計画変更にも柔軟に対応できるでしょう。資材や機材調達の効率化・最適化も可能です。
また、現場での危険箇所や作業範囲をモデル上で確認し、作業員への指示を的確に行えるため安全管理の向上にもつながります。
3|維持管理段階での活用
BIM/CIMは、維持管理段階における重点点検箇所の可視化や資料検索の効率化、損傷箇所や意思決定の迅速化にも活用されます。
対象構造物の3次元モデルに点検データや履歴情報を統合することで、迅速かつ正確に必要な情報を取得できます。たとえば、定期点検の際には、モデルを使って劣化箇所や補修が必要な部分を特定でき、作業計画の効率化が可能です。
また、過去の修繕履歴や材質情報を確認することで、最適なメンテナンス方法を選択できます。紙媒体やデジタルデータでばらばらに保管されている場合に比べ、素早く工事に着手できるでしょう。
BIM/CIMをより高度に活用するための「点群データ」とは?
点群データとは、『XYZの位置座標、RGBの色情報や輝度情報、法線ベクトル情報等、様々 な情報が付加された点』の集合体データのことです。 見た目は3Dモデルに見えますが、拡大すると細かな点で構成していることが見えます。
BIM/CIMにおいて必須ではありませんが、より高度な活用を目指す場合に利用されます。このデータは、3Dレーザースキャナーやハンディスキャナーを使った3次元測量で作成され、建物や地形の詳細な情報を正確に記録できます。
点群データの利点は、その高精度な情報です。BIM/CIMも物体の形状は表現できますが、細部まで表現できないことがあります。そのため、既存建物のリノベーションや、複雑な地形を伴うインフラプロジェクトの設計など、細部の形状まで表現したいときは点群データの活用が効果的です。
また、BIM/CIMに統合することで、現場の状況を忠実に再現でき、施工計画の精度をより高めることができます。
BIM/CIMの情報収集に役立つWebサイト(国土交通省・JACICなど)
BIM/CIMに関する情報収集には、信頼性の高いWebサイトの利用をおすすめします。具体的なWebサイトは次のとおりです。
・国土交通省のポータルサイト
・JACIC(一般財団法人日本建設情報総合センター)
・CIVIL USER GROUP
1つ目の国土交通省のポータルサイトは、公的機関が提供するBIM/CIMの基本情報や国土交通省の取り組み、ガイドラインなどを確認できるWebサイトです。導入事例や研修コンテンツも掲載されており、実務に直結する情報を得られます。
2つ目は、JACIC(一般財団法人日本建設情報総合センター)のWebサイトです。ここでは、各建設分野におけるBIM/CIMの活用事例やBIM/CIMの活用効果、課題などが掲載されています。
3つ目は、CIVIL USER GROUPのWebサイトです。土木分野でのBIM/CIM普及を目的としており、セミナー開催の案内や3次元部品モデルのダウンロードなどが提供されています。
このようなWebサイトを利用することで、BIM/CIMに関する知識を効率的に収集し、実務に活用できるでしょう。
BIM/CIMの導入を検討する際の注意点
BIM/CIMの導入を検討する際の注意点は、次の2つです
・自社に合ったソフトウェアを選定する
・適切なスペックのパソコンを用意する
各項目の詳細を解説します。
1|自社に合ったソフトウェアを選定する
BIM/CIMを導入する際は、自社に合ったソフトウェアを選定することが重要です。まず、作成するモデルの種類を明確にする必要があります。BIM/CIMのモデルは、次の6種類です。
・地形モデル
・地質・土質モデル
・線形モデル
・土工形状モデル
・構造物モデル
・統合モデル
業務で扱うモデルを確認したうえで、必要なソフトウェアを選択します。
また、ソフトウェアが自社の目的や用途に合った機能を持っているかを確認することも大切です。たとえば、対外説明を重視する場合は、分かりやすい可視化機能やシミュレーション機能があるとよいでしょう。さらに、国土交通省が定める要件を満たしているかを事前に確認しておくと、後のトラブルを防ぐことができます。これらのポイントを考慮して選定することで、期待した成果を得やすくなるでしょう。
2|適切なスペックのパソコンを用意する
BIM/CIMソフトウェアは、3Dモデリングやレンダリング、解析といった処理を行うため、高性能なパソコンが求められます。購入する際は、使用するソフトウェアの推奨スペックを目安にするとよいでしょう。
推奨される大まかなスペックの例は、次のとおりです。
| パーツ | 推奨スペック例 |
| CPU | ・Intel® Xeonシリーズ ・Intel® Core™ i7以上 ・AMD™ Ryzen 7以上 |
| メモリ | 32GB以上 |
| グラフィックス(GPU) | ・NVIDIA RTX Aシリーズ ・NVIDIA RTX 3060以上 など |
| ストレージ | SSD(NVMe)1TB以上 |
上記に加え、パフォーマンスの低下を防ぐために、冷却性能の高いパソコンを選ぶことも重要です。
BIM/CIMの活用におすすめ!マウスコンピューターのパソコン・ワークステーション3選!
マウスコンピューターは、スペックをカスタマイズできるBTO(Build To Order)パソコンを販売しています。ここからは、BIM/CIMの活用におすすめできる、マウスコンピューターのパソコン・ワークステーション(高い処理パフォーマンスを発揮するコンピューター)を3機種ご紹介します。
※ 製品の情報や価格は2026年1月13日時点の情報となります。
1.NPUを搭載したクリエイター向けモデル「DAIV FX-I7N10」
| OS | Windows 11 Home 64ビット (DSP) |
| CPU | インテル® Core™ Ultra 7 プロセッサー 265K |
| グラフィックス | NVIDIA RTX™ A1000 |
| メモリ標準容量 | 32GB (16GB×2 / デュアルチャネル) |
| M.2 SSD | 1TB (NVMe Gen4×4) |
| 通常価格 (税込) |
469,800円 |
|
DAIV FX-I7N10
この製品を詳しく見る
|
|
DAIV FX-I7N10は、高性能なCPUやグラフィックス(GPU)を搭載したワークステーションです
CPUには、AI(人工知能)処理専用のNPU(Neural Processing Unit)を備えたインテル® Core™ Ultra 7 プロセッサーを採用しており、AIタスクを効率的に処理できます。
グラフィックス(GPU)は、 2,304基のCUDA®コア、72基の第3世代Tensorコア、18基の第2世代RTコアを組み合わせた、NVIDIA RTX™ A1000を搭載しており、3次元モデル構築における生産性を高めてくれます。
2.多様な分野で活躍するモデル「DAIV FW-X3N04」
| OS | Windows 11 Pro for Workstations 64ビット (DSP) |
| CPU | インテル® Xeon® w3-2423 プロセッサー |
| グラフィックス | NVIDIA RTX™ A400 |
| メモリ標準容量 | 64GB (16GB×4 / クアッドチャネル) |
| M.2 SSD | 1TB (NVMe Gen4×4) |
| 通常価格 (税込) |
809,800円 |
|
DAIV FW-X3N04
この製品を詳しく見る
|
|
DAIV FW-X3N04は、ワークステーションに適したOS(Operating System)を搭載したモデルです。Windows 11 Pro for Workstationを採用しており、膨大なデータの高速処理やサーバーレベルのセキュリティを可能にします。
また、3Dモデリングや機械学習などで高いパフォーマンス発揮するインテル® Xeon® w3-2423 プロセッサーや、プロフェッショナル向けのグラフィックス(GPU)、NVIDIA RTX™ A400を搭載しており、BIM/CIMの活用をサポートしてくれます。
さらに、ケースファンを最大6個搭載できたり、電源ユニットにCPU用の大型ラジエーターを搭載できたりなど、冷却性能も高いワークステーションです。
3.ワークステーションに最適なOSを搭載したモデル「DAIV FW-X3N10」
| OS | Windows 11 Pro for Workstations 64ビット (DSP) |
| CPU | インテル® Xeon® w3-2423 プロセッサー |
| グラフィックス | NVIDIA RTX™ A1000 |
| メモリ標準容量 | 64GB (16GB×4 / クアッドチャネル) |
| M.2 SSD | 1TB (NVMe Gen4×4) |
| 通常価格 (税込) |
879,800円 |
|
DAIV FW-X3N10
この製品を詳しく見る
|
|
DAIV FW-X3N10は、BIM/CIMを使った業務を効率化できるプロフェッショナル向けのワークステーションです。
グラフィックス(GPU)に負荷のかかる作業の高速処理に対応するワークステーション向けOSや、3DCG制作に高いパフォーマンスを発揮するグラフィックス(GPU)を搭載しています。また、マザーボードのチップセットにはW790を採用しており、DDR5メモリやM.2 SSDに対応しています。
クリエイター向けパソコン「DAIV」をご購入いただいたお客様の声
まとめ:BIM/CIMを活用した業務の効率化を目指そう!
BIM/CIMは3次元モデルを活用し、調査や計画、設計から施工、維持管理まで情報を一元管理し、各業務プロセスを効率化する手法です。設計段階での合意形成や施工現場での手戻り防止、安全管理が容易になり、維持管理段階でも迅速な情報共有ができます。
BIM/CIMを効果的に活用するには、適切なソフトウェアと目的に合うパソコンを選定することが大切です。
マウスコンピューターでは、プロのエンジニアにおすすめのワークステーションを販売しています。スペックのカスタマイズもできるため、希望に合ったモデルの購入が可能です。詳しい製品情報は、下の公式サイトからご確認ください。